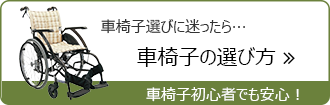密かな優しさとスロープ
車椅子のクラスメイト

-
体に障がいを持つ人と関わる機会というものは、
案外あるようでないものではないでしょうか。
なんとなく自分とはあまり関係の無い話だと、テレビで見るような
話だと思っている人も少なくないかもしれません。
私も中学まではそういった気持ちでいました。
周りは当たり前のように皆五体満足で、特に体が弱かったりという仲間もいませんでした。
一緒に遊ぶこと、出かけること、学ぶことが当たり前。
皆一緒が当たり前。そんな感覚で過ごしていました。
そんな意識が変わったのは、高校に入学してからのことです。
こんな身近に障がいを持つ人が現れるとは思ってもみませんでした。
私が入学したのは私立の女子高です。
歴史ある古い校舎と、校門に建てられた設立者の銅像が目印の、いわゆる「お嬢様学校」でした。
挨拶や目上の方への対応にはとても厳しい学校で、
淑女としての在り方、佇まいを細かく指導されていました。
そんな学校ではありましたが、やはりどこにでもいわゆる
「不良」は居るもので、当時も同学年に数名「怖い雰囲気」を醸し出している人がいました。
髪型や制服の着方、授業中の態度や先生方への接し方など、
事あるごとに注意されている様子を、いつも遠巻きに眺めていたものです。
そんなある日、私のクラスに転校生がやって来ました。
その子は、一度見たら忘れられないような特徴のある子でした。
なぜなら、車椅子に乗っていたからです。
クラスの不良の態度に

-
肌は青白く少しぽっちゃりとした外見と、あまり笑わなそうな
暗いイメージと、無機質な車椅子のその様子は瞬く間に話題になってしまいました。
当時はバリアフリーが今のように充実しておらず、
私の学校にもそのような設備は整っていませんでした。
幼い頃に事故で両足の機能を失ってしまったというMさんは
身の回りのことはほとんど自分で出来るようでしたが、
唯一階段を上ったり降りたりする際は人の手を借りなければなりません。
数人で車椅子を抱えて移動するのです。
初めのころは主に男の先生がその役割をしていましたが、
Kさんがクラスに馴染んでくるとクラスメイトたちが交代で手伝うことになりました。
なんせ車椅子を見ること自体が初めての私たち。
戸惑いながら恐る恐るといった感じで手伝っていたのですが、
徐々にそれが「私達の使命」のように思えてきました。
皆が率先して車椅子を抱える役割を果たそうとしていましたが、
クラス内の「不良」と呼ばれているメンバーたちは決して手伝おうとしませんでした。
それどころか、「遅い」「邪魔」という言葉を口に出すことさえあったのです。
私達のほとんどがそんな彼女たちに対して
憤りを感じていましたが、誰も直接注意することはありませんでした。
階段にできた手作りのスロープ

-
Kさんも、「私のせいで嫌な思いをさせている」と、
申し訳なさそうに俯きながら階段を抱えられていました。
そうして数ヶ月が過ぎた頃、学校の入り口にある短い階段に手作りのスロープが設置されたのです。
技術の先生の手作りの木のスロープ。
それが設置されたということ自体が私たちにとっては大ニュースでした。
まだまだ介助しなければならない場面のほうが多いけれど、
そのスロープが設置された一箇所だけは自分で上ることが出来ると、Kさんは顔を綻ばせて喜んでいました。
Kさんにとって、クラスメイトに迷惑をかけているという
気持ちはどうしてもあるようで、玄関だけは自分で…。
という意思でそこを通っているようでした。
私たちも、あえてその部分だけは手を貸さないようになりました。
そんなある日、部活ですっかり遅くなって帰ろうとしていたときのことです。
玄関で靴を履き替えようとしていると、例の不良グループが
スロープに腰をかけて雑談している様子が目に入りました。
出来るだけ関わりたくないメンバーでしたので、出るに出れずにいた私。
彼女たちが早くそこから去ってくれないだろうかと
ヤキモキしていると、そこに技術の先生が通りかかりました。
陰ながら行われた優しさ

-
彼女たちを注意してくれることを祈りながら様子を見ていると、こんな言葉が聞こえてきました。
「先生、これ(スロープ)作ってくれてありがとう。でもここちょっと歪んでてだめだよ」
そう言ってスロープの不備を指摘しているのです。
思わず身を乗り出すようにして聞いてみると、なんと、
そのスロープの設置を学校側に打診したのが彼女たちだったのです。
手伝ってあげるだけでは女子の力では限界がある。
もっと学校側に出来ることがあるはずだ、と、彼女たちが訴えたのだということがわかりました。
私たちが、誰よりKさんが一番喜び、必要としていたものを生み出すきっかけが彼女たちの声だったのです。
そして、「私たちが頼んだことは、絶対に誰にも言わないように」と念を押している声まで聞こえて来ました。
それは彼女たちの精一杯の応援と優しさ、そして強がりだったのでしょう。
その後も彼女たちがKさんを手伝うようなことはありませんでしたし、
相変わらずでしたが、もう彼女たちを「不良」という目で見ることはありませんでした。
誰よりも優しく、恥ずかしがり屋だということが分かってから、自分の中でも何かが変わったようでした。
そして、ただ手を貸すだけが優しさではないのだということを彼女たちに教わったような気がしたのです。